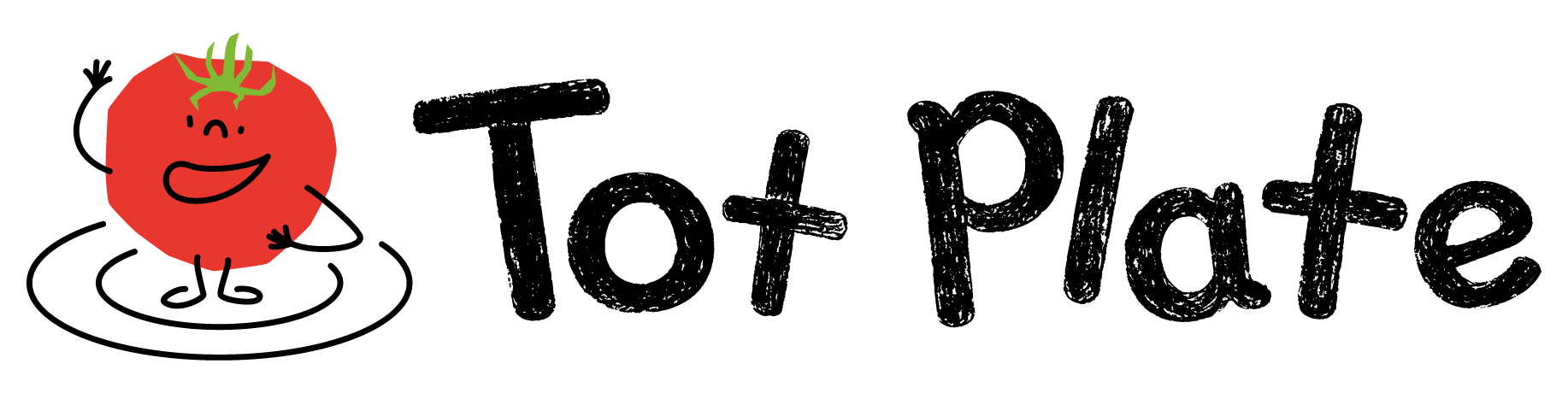【栄養士が教える!】離乳食に使える調味料とは?月齢ごとの目安や味付けのポイントを紹介


離乳食が薄味の理由

まだいろいろな食材に慣れていない赤ちゃんにとって、濃い味付けの食事を食べることは腎臓に大きな負担になってしまいます。また小さいころに濃い味付けに慣れてしまうと、大きくなってからも塩分や糖分、カロリーが高い食生活になってしまい、生活習慣病などのリスクも上がってしまいます。
赤ちゃんの頃は味を感じ取る味蕾が大人よりも多いので、薄い味でも味を感じ取ることができるそうです。小さいころから素材の味や薄味に慣れておきたいものですね。
離乳食の味付けはいつから?

離乳食初期(生後5〜6ヶ月)の味付け
離乳食初期では、味はつけずに素材の味をいかしましょう。スープなどは野菜から出ただしで十分です。
このころは赤ちゃんにとって初めて口にするものが多いでしょう。安全を重視して素材の味を味わってもらうことも大切です。
離乳食中期(生後7〜8ヶ月)の味付け
この時期もまだ味付けは必要ありません。風味をつけたい場合は、かつおだしなど動物性のだしの使用も可能になります。7ヶ月頃からバターも少量でしたら食べさせても大丈夫な時期です。
味付けをする場合は風味付け程度を意識して、アレルギーなどにも注意しながら味付けをしましょう。
離乳食後期(生後9〜11ヶ月)の味付け
このころから少量の塩、砂糖、醤油、味噌なども使うことができるようになります。基本は薄味を忘れずに、味付けのバリエーションを増やすのもよいですね。
必ずしも、味付けをしなければならないわけではないので、赤ちゃんが味付けなしで食べてくれる場合は無理に味付けをしなくても大丈夫です。
離乳食完了期(1歳~1歳6ヵ月)の味付け
完了期になると、はちみつやめんつゆ、ソースや酢など、さらに使用できる調味料のバリエーションが広がります。使える調味料は増えますが、まだ基本は薄味です。香辛料など刺激が強い調味料も控えましょう。
調味料を使うときのポイント

風味が出る程度の少ない量を使用する
赤ちゃんは味蕾が多く、大人よりも味を感じることができます。舌を育てるためにも、味付けは風味付け程度にしておきましょう。
離乳食向けの調味料・だしを使用する
大人と同じ調味料では塩分や添加物が心配な時もありますね。そんな時は離乳食向けの調味料やだしを利用しましょう。
1歳向けのソースやマヨネーズも販売されていますので、上手に使い分けることがおすすめです。
離乳食完了期におすすめ!調味料を使ったレシピ3選

レシピ1.きび砂糖の蒸しパン
(材料)10個分
- 薄力粉 120g
- ベーキングパウダー 5g
(アルミフリー)
- きび砂糖 30g
- プレーンヨーグルト 120g
- かぼちゃ 400g
(作り方)
- 1. 薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておく。
- 2. かぼちゃは皮と種を取り除き、柔らかく茹でて潰しておく。
- 3. ボウルにきび砂糖とヨーグルトを混ぜ合わせる。
- 4.1を加えて混ぜ合わせ、2のかぼちゃを加えて混ぜ合わせる。
- 5. アルミカップに分けて、蒸し器で15分ほど蒸す。
レシピ2.豆腐ドレッシング
(材料)
- 豆腐 200g
- 酢 大さじ1/2
- 塩 小さじ1/2
- オリーブオイル 50cc
(作り方)
- 材料を全て、ミキサーにかける。
- 市販のマヨネーズが心配な方に。野菜スティックなどと相性がバッチリです。
レシピ3.厚揚げの煮物
(材料)
- 厚揚げ 40g
- 人参 30g
- 大根 30g
- だし汁 100cc
- 砂糖 少々
- しょうゆ 少々
(作り方)
- 1. 人参と大根は8㎜角に切って、柔らかく茹でておく。
- 2. 鍋にだし汁と1の野菜、厚揚げを入れて弱火で3分ほど煮る。
- 3. 砂糖としょうゆを入れて、弱火で5分ほど煮る。
離乳食 完了期 調味料に関するよくある質問

質問1.薄味でも食べてくれますが味付けするべきでしょうか?
味付けは必ずする必要はありません。赤ちゃんが味付けをしなくても食べてくれるならば、濃い味に慣れさせないためにも、味付けはしなくても大丈夫です。
塩分など調味料に含まれる栄養素は他の食材からも摂取できますし、赤ちゃんが素材の味を味わうためによく噛かむことで、唾液の分泌量も増え味覚も育ちます。
質問2.食べてくれない場合、味付け以外に気をつける点はありますか?
固さや大きさなどに変化をつけると食べてくれるかもしれません。手づかみや赤ちゃんが自分で食べやすい用に工夫してみたり、お皿やスプーンを変えてみることで食べてくれるようになることもあります。
まとめ

味付けのバリエーションが広がることによって、赤ちゃんの食への意欲がますます高まりますね。赤ちゃんがよく食べてくれるからと、味付けを濃くしすぎてしまうのは要注意です。
赤ちゃんの味覚を育てるためにも、薄味を基本にいろいろな味に触れさせてあげましょう。